
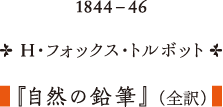
第4分冊 (XVI-XVIII) | 第5分冊 (XIX-XXI) | 第6分冊 (XXII-XXIV) | 解説|
写真術発明略史
新たな〈技術〉によるいくつかの実例をここにお目にかけるにあたって、その〈技術〉を発見するにいたった経緯を簡単に説明しておくべきであろう。事情はおおよそ以下の通りであった。
1833年10月初めのある日、私はイタリア、コモ湖の美しい畔にいた。そこで私はウォラストンのカメラ・ルシダを取り出して機嫌よくスケッチをしていた。いや、スケッチをしようとしていた、というべきだろう。というのも、そのスケッチはちっともうまくいかなかったからである。プリズムをのぞき込んでいるあいだはすべてが美しく見えるのに、目をそこから離すと、思うにまかせない鉛筆が紙のうえに見るに堪えない描線を残しているだけだったのである。
あれこれ試してはみたもののうまく行かないので、私はその器具を放り出し、こういう結論するにいたった。この器具を使うにもまずはドローイングの心得が必要で、あいにく私にはそれが欠けているのだと。
そこで次に私が考えたのは、何年も前に試したある方法をもう一度試してみることであった。〈カメラ・オブスキュラ〉を使うという方法がそれで、この器具のガラス板に透明なトレーシング・ペーパーを敷き、そこに対象物の映像をピント調整して映し出すのである。この紙に対象物がくっきりと見えるので、ある程度正確に鉛筆でそれをなぞることができるわけである――とはいっても相当に時間もかかるし骨も折れはする。
私は1823、24年にイタリアを訪れた際、この単純な方法をすでに試みたことがあった。だが、実際に使ってみると、うまく扱うのはなかなか難しいと気づいた。紙に手と鉛筆の力がかかるせいでどうしても器具がぐらついて位置がずれてしまうからである(道路脇で、あるいは宿屋で窓越しに慌ただしくスケッチするときなどは、たいてい設置の具合が悪く、がたがたするのだ)。そして器具の位置はいったん狂ってしまうと、元の方向にきちんと向け直すのはひどく難しい。
それに加えてもう一つ難点があった。つまり、紙のうえに見える微小な細部をすべてなぞるのは、〔私のような〕アマチュアの技量と根気ではおぼつかないのである。こうしたわけで、実際のところ、そのアマチュアが持ち帰ることができるのは、その光景を思い出すよすがといった程度の代物でしかない――それでも、ずっと後になって振り返るときには価値が出てくるのは確かであるが。
これが、そのときに私が再度試みようと思った方法である。私は、以前そうしたように、紙の上に描き出される光景の輪郭を自分の鉛筆で苦労してなぞってみようと思ったのである。そんなことを思っているうちに私がじっと脳裏に浮かべることになったのは、〈カメラ・オブスクラ〉のガラスのレンズが紙の上に投じるピントのあった画像、自然が描くその画像の比類のない美しさのことであった――妖精のようにはかない画像、瞬間が作り出し、そうかと思えばすぐに消え去ることを運命づけられた画像。
こうした思いに耽っているときに次のような着想 idea が浮かんできたのである…… もしこうした自然の映像が紙のうえに自らを押印してそこに留まり、定着されるとしたら、それはなんと素晴らしいことだろう!
それが不可能だとどうしていえよう? ――そう私は自問したのである。
その画像とは、それに纏わるさまざまな観念を剥ぎ取り、その根本にある本性に絞って考察するならば、要するに、紙のある部分には強い光が、別の部分には深い影が投げかけられることで生じる光と影の継起ないし多様な取合わせにほかならない。さて、〈光〉はそれが当たる場所に作用を及ぼすことがあり、一定の状況のもとでは、実際、物体自体に変化を引き起こすほどの作用を及ぼす。そこで、そうした作用が紙に加わるとしよう。そうしてその紙がそれによって眼に見える変化を被るとしよう。その場合、結果として生じるなんらかの効果は、間違いなくそれを生み出した原因とおおよそ類似したものになるはずである。したがって、光と影の変化に富む光景は、紙に作用した光の強弱に応じて紙の各所に強弱さまざまな映像ないし刻印を残すことになるだろう。
私の頭に浮かんできたのはこうした着想であった。それ以前にも、とりとめもない哲学的夢想に耽っている最中に思いついたことがあったのかどうか、それは分からないが、たぶんあったに違いなかろうと私は思っている。その着想はこのとき実に強力に私に襲いかかってきたからである。当時私は古代イタリアの史跡巡りをしていたから、むろんこうしたきわめて難しい研究を始めることはできなかった。だが、そのとき考えたことをイングランドに帰国する前に忘れてしまわないように、私は丁寧に文字にして書き留めた。それに加えて、もしそれを実現できるとすれば、そのために最もうまく行きそうな実験についても書き留めておいた。
化学者の著作によれば硝酸銀は光の作用に特別に反応する物質であるので、イングランドに戻ったらできるだけ早く、まずこれを最初に試してみようと私は決めていた。
しかし、化学の本を通じて硝酸銀が〈光〉によって変化を被り分解されるという事実は知っていたものの、私はまだ実際に実験してみたことは一度もなく、それゆえ、その作用が早いのか遅いのか、まったく見当もつかなかい状態であった。だがそこは根本的に重要な点で、というのも、もし遅かったら、私の理論は単なる哲学的な夢想ということで終わってしまったかもしれないのである。
いま私が思い出せる限りでは、以上がおおよそ私が写真の理論を思い付くに至るまでの思索、私を最初に自然の秘密のなかにかくも深く隠された一筋の小径を探るべく促した思索の内容である。そして、その後なされた数々の研究は――それらがどれほど成功したと考えられるとしても――この最初の独創的な着想の価値に匹敵しうるようなものではないと私は考えている。
1834年1月、私は大陸旅行を終えてイングランドに帰国し、その後すぐに私の理論と予測を実験で試し、それに現実的な基礎があるかどうか調べてみることにした。
そこで私はまず硝酸銀溶液を調達し、刷毛を使ってその溶液のいくらかを一枚の紙全体に塗り広げ、そののちその紙を乾燥させた。この紙を日光にさらしてみたところ、残念なことに効果が生み出されるスピードが予想よりずっと遅いことが分かった。
私は次に塩化銀を試すことにした。析出したての塩化銀をまだ湿っているうちに紙全体に塗り広げた。だがこれも、硝酸銀の場合と変わるところはなく、太陽にさらすとゆっくりと暗い紫に変色していった。
塩化銀を作ってから紙に塗り広げるのは止めにして、今度は次のような方法に変えてみた。まず紙に濃い食塩水を薄く塗布し、それが乾いたら、もう一度硝酸銀を薄く塗布するのである。こうすると、もちろん、塩化銀が紙に作られることになるが、この実験の結果も前のものとほとんど変わらず、塩化銀はこのような方法で作られても眼に見えて感度が高くなることはなかった。
もっとましな結果が得られないものかと同様の実験を何度も繰り返した。使用する溶剤の比率をあれこれ変えてみたり、食塩ではなく硝酸銀を先に使ってみたり、等々。
こうした実験の中には慌ただしく行ったものも少なくなかった。そういう場合などには、刷毛が紙全体に渡り切らないことがあり、そうするともちろん、結果としてムラが生じることになった。紙の一部がその他の部分よりもずっと速く日光に反応して黒変するのが何度か観察された。このより感度の高い部分は、たいてい、刷毛で〔食塩水を〕しっかり塗布した部分の端、つまりそこを取り囲む縁の近くだった。
この現象がどうして生じたのか、その原因をあれこれ考え抜いた末、私はこう推測した。このへりの部分は、吸収した塩の量が少なかったために、なんらかの理由で、光に対する感度が高くなったのではないかと。この思いつきの正否を実験で確かめるのは簡単であった。一枚の紙を、普段使っていたものよりずっと薄い食塩水で湿らせ、乾燥後、硝酸銀を薄く塗布した。この紙を日光にさらすと、たちまち、それまで私が見てきたものより格段に高い感度をはっきり示し、紙の表面全体がみるみる均等に黒化していったのである。こうして重要な事実、すなわち塩が含まれる量が少ないほうがより大きな効果を生み出すという事実が一挙に、疑いの余地なく立証された。これは予期しない事態であったが、これによって、なぜ先行する研究者たちが塩化銀についての実験のなかでこの重要な結果を見逃してきたのか、そのわけも簡単に説明がつくことになる。つまり、彼らは実験を行う際、塩と銀の比率をいつも間違えていたのである。彼らは、完璧な塩化物を作るために塩をふんだんに使用していたのだが、なすべきことは実は(いまでははっきりしたことだが)、塩を減らして不完全な塩化物を作ること、もしくは《亜塩化》銀(むしろこう呼ぶべきかもしれない)を作ることだったのである。
塩をやたら大量に使ってしまうと、紙に及ぶ光の作用を促進するどころかむしろ逆効果で、光の作用をすっかり弱め、その効果をほとんど消滅させてしまう。だからこそ、食塩水に浸す作業が、後には、感光紙にさらに光の作用が及ぶのを防ぐ定着法として利用されるまでになったのである。
ごく薄い食塩水を使って亜塩化銀を作るというこの工程を私は1834年に発見したのだが、これを使えば、木の葉やレースのような複雑な形と輪郭をもった平らな物については、太陽の光にさらすことで難なくその判明で実にきれいな映像を得ることができた。
私はまず紙を充分乾燥させ、そのうえに木の葉などを平らに広げて置き、ガラスで覆って上から押さえて密着させ、その後日なたに出した。紙が暗色に変わったところで、すべてを日陰に移し、物を紙から取りのぞいた。すると、それらの物の映像がきわめて完全なかたちで、また美しく紙のうえに刻印され、あるいは輪郭づけられていたのである。
しかし、感光紙を〈カメラ・オブスクラ〉の焦点面に置き、それをなんらかの対象――たとえば何かの建物――に向けたまま、1、2時間ほどの適度な時間待ってみても、紙のうえに生じる効果はあまり強くなく、期待どおり満足のいく建物の画像を呈示するには至らなかった。屋根や煙突などの輪郭は空を背景にしてくっきり浮かび上がっているが、建築の細部はかすんでいて、陰の部分などは白地のままか、ほぼそれに近い状態であった。したがって、光に対する紙の感度は、見方によっては相当高いとも考えられたものの、しかし、〈カメラ・オブスクラ〉を使って画像を得るという用途のためには明らかにまだ不十分であることが分かった。そこで、もっときちんとしたなんらかの結果を得るために、実験の方針を再び更新しなければならなくなった。
この研究を続行するための充分な暇が次に出来たのは、1834年の秋、ジュネーヴ滞在中のことであった。春に行った実験をそのとき繰り返し、あれこれと条件に変化をつけてみた。以前偶然お会いしたことのあるH・デイヴィ卿が《ヨウ化》銀のほうが《塩化》銀よりも光に対する感度が高いと書いているのを読んで驚き、ヨウ化銀で試してみることにした。実験してみると、非常に驚いたことに、正反対の「事実」が明らかになった。ヨウ化銀は、塩化銀よりも感度が低いばかりか、光にまったく感応しなかったのである。実際のところ、ヨウ化銀はどれほど強烈な日光にさらしても完全に無感応であった。日光にどれだけ長時間さらしても、元の色味(かすかな藁色)のまま変化することがなかったのである。この事実が教えてくれたのは、この特殊な主題に関しては化学者の著作はほとんど頼りにならず、実際に実験してみたこと以外何も信用してはいけないということであった。というのも、デイヴィ氏がなんらかの条件のもとで彼が記述している事象を観察したのは疑いえないとしても、しかし、彼が観察した事象が、なにか規則に反する例外のようなもので規則そのものではない、ということも明らかであったからである。事実、さらに研究を進めた結果分かったことは、デイヴィ氏が観察したのは、ヨウ素が銀に対して不足している亜ヨウ化銀のようなものに違いないということであった。というのも、ちょうど塩化銀と亜塩化銀では、塩化銀のほうがずっと感度が低いように、ヨウ化銀と亜ヨウ化銀とのあいだでもよく似たコントラストがあり、しかもそのコントラストの度合がとても強く、完全に対立するものだからである。
しかしながら、こうして発見された事実は早速役立つものであることが判明した。というのも、ヨウ化銀が光に感応しないことが分かったので、しかも塩化銀はヨウ化カリウム溶液の中に浸すことで簡単にヨウ化銀に転化されるので、塩化銀を用いて作られた画像は、それをそのアルカリ金属性のヨウ化物〔=ヨウ化カリウム〕の溶液にさっと潜らせることで《定着》が可能だということになるからである。
この定着法は簡単なもので、きわめて首尾よく行くこともあった。しかし、多くの場合には欠陥があり、その欠陥は時間が経ってからでないとはっきり分からないものだった。その欠陥とは、新しい予期せぬ原因に依るもので、すなわち、画像がその定着法によって処理されると、太陽光線による《黒変》の効果からは守られるのだが、しかし逆の効果、つまり《白変》にさらされてしまうのである。その結果、何日か経つと、画像の暗い部分が褪せ始め、さらに時間が経つにつれ画像全体が消え、ついには紙が一様に薄黄色になってしまうのである。多くの成功した画像がこの運命から免れたことは間違いないが、しかし、それらもいずれすべてそうなりかねず、ヨウ素による定着法は、写真製法として使用するにはあまり確実なものではないと考えねばならない。ただ、いくつかの点に細心の注意を払って用いれば大丈夫なのだが、ここでそれについて述べるのは長くなりすぎよう。
1835年夏、イングランドは燦々たる晴天に恵まれ、私は、〈カメラ・オブスクラ〉で建物の画像を得るための新たな試みを行った。私が新たに考案した方法とは、紙に塩と〔硝酸〕銀とを交互に繰り返し薄く塗布し湿ったままの状態でそれを使用することによって、紙の感光性を追加するというもので、これによって私は、〈カメラ・オブスクラ〉を使って映像を得るために必要な時間を、天気のよい日なら、10分にまで短縮することに成功した。しかし、それらの画像は、とてもきれいではあるのだが、とても小さくミニチュア同然であった。もっと大きなサイズのものも得られはしたが、しかしそれらは、たいそう根気を必要としたし、小さい画像ほど完全なものには見えなかった。というのも、装置を同じ対象に向けたまま長時間しっかり固定することは難しく、紙も湿った状態で使うため、効果にムラが現れることが多かったからである。
その後の3年間は、それまでの知識に大して何も付け加わることはなかった。実験を行うための充分な暇がなかったことが大きな障害、妨害で、そのため私は、当時の不完全な状態のままこの〈技術〉の報告を公表しようとほとんど心を決めていた。
それまでに得ていた結果がどれほど興味深いものであるにせよ、しかし私は、もっとはるかに重要なことがなおその背後に残されており、この事象の迷宮を解明する鍵はまだ見つかっていないと確信してはいた。しかし、すぐにはこれ以上の成功を収める見込みもなさそうであったので、その時点ですでに行っていたことについて短い報告論文を書き、〈英国王立協会〉に提出しようと考えたのである。
しかしながら、1838年の暮れに、私はまったく新しい種類の注目すべき事象を発見した。一枚のガラス板のうえに一枚の銀箔を広げ、そのうえにヨウ素の粒をおく。すると、その粒を中心として色の環が形成されることが観察されたのである。ガラス板をわずかに暖めると、とりわけそうであった。色の環については、ヨウ化銀のごく薄い層が形成されたせいだと難なく考えることができる。しかし、まったく予期せぬ現象が、銀板を窓の近くに置き、光のなかにもっていたときに生じたのである。というのは、そのとき、色の輪がたちまち変色し、「薄膜の色」としてはそれまで見たことのないような、とても珍しい別の色合いを呈したのである。たとえば、銀板の、最初は薄黄色に光っていた部分は、昼光のもとにもたらされると、オリーヴ・グリーンに変色した。この変化はさほど速くはなかった。私がそれまで使っていた感光紙の変化と比べるとずっと遅いもので、それゆえ、この新しい現象の美しさを堪能したのち、私はしばらくそれらの実例をそのままにして、同じ見かけを保持するものかどうか、それとも、さらに変質してしまうかどうか見極めようと思ったのである。
以上が、1838年の暮れの時点でこの研究において私が成し遂げた進歩であったが、そのとき、科学界に事件が起こり、その事件が、ほぼ5年にわたってこの長く複雑な、しかし興味深い一連の実験を進めながら私が温めてきた望み――すなわち、世界に〈新たな技術〉、その後〈写真〉と名づけられることになるものの存在を最初に告知したいという望み――をくじいてしまったのである。
私が言おうとしているのは、もちろん、1839年1月に、ダゲール氏の大いなる発見、つまり彼がダゲレオタイプと名づけた写真製法が公表されたことである。この素晴らしい発見の最初の告知――というより(実際に用いられる方法はさらに何ヶ月ものあいだ秘密のままにされたのだから)むしろ発見されたという事実の告知――によって世界中の至る所で引き起こされた騒動については私がわざわざ語るまでもない。その発見が突如として大きな評判を得たには2つの原因がある。第1に、発見そのものの素晴らしさである。第2に、アラゴーの熱意と熱狂である。彼は私的な友情によって鼓舞されて、嬉々としてこの新たな技術の発明者〔ダゲール〕を、あるときはフランスの科学者の集まりである〈学士院〉で、また別のときには、科学的判断という面では劣っていても愛国心の強さという面では劣ることのない〈代議院〉で雄弁に賞揚したのである。
しかし、〈写真術〉の初期段階を明らかにするこの小論がダゲレオタイプの告知という重要な時期に到達したところで私は一旦筆を措き、この〈技術〉のその後にたどった歴史については今後発行する分冊のなかで記すことにしたい。
